小学生の子どもを持つお母さんにおすすめの本!37のヒントで子育てや親子関係の悩みが楽になる/感想/みんなの評価・クチコミは?
子育てをしていると、様々な悩みに直面しますよね。
「うちの子、このままで大丈夫かな?」
「もっと何かしてあげられることはないのかな?」
そんな風に思っているお母さんに、ぜひおすすめしたい一冊があります。
それは、工藤勇一先生の「麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること」です。
この本は37のヒントを通して、子育てや親子関係の悩みを解決したり、軽くしたりするためのヒントを与えてくれます。
私も実際に読んでみて、心が軽くなったと感じました。
今回は、この本の感想と、特におすすめしたいポイントをご紹介します。
「麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること」作品情報
| タイトル | 麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること |
|---|---|
| 著者 | 工藤勇一 |
| 発行日 | 2019年10月17日 |
| ISBN | 9784761274498 |
| サイズ | 188mm×130mm |
| ページ数 | 216ページ |
| 内容紹介 |
「子育ての本当の目的」について、麹町中学校の工藤勇一校長が「当たり前」を問い直す。友達関係、不登校、親子関係、成績など、親が抱える悩みに寄り添い、心を軽くするヒントが満載。
|
| 著者紹介 |
1960年山形県鶴岡市生まれ。東京理科大学卒業後、公立中学校教師、教育委員会勤務を経て、2014年より千代田区立麹町中学校長。教育改革で注目を集め、教育再生実行会議委員なども歴任。
|
| おすすめポイント |
* 子育ての「当たり前」を見直すきっかけになる * 親の不安を軽くするヒントが満載 * 麹町中学校の実践例が参考になる
|
| おすすめ読者 |
* 子育てに悩んでいる親御さん * 子どもの生きる力を育みたい親御さん * 教育に関心のある方
|
37のヒントが詰まった目次
本の帯にある「心が軽くなる」という言葉は、まさにその通りでした。
読み始めた時の息苦しさが和らいだのを覚えています。
まず、目次を見ただけでも、たくさんの気づきや発見がありました。
- 子どもはもともと主体的な生き物
- 手をかけないほど、子どもは自律する
- 不幸になるなら「理想の子育て論」はいらない
- 子どもは思うようには育たない
- どんな環境でも挑戦できる強い脳はつくれる
- 親はいい加減くらいでちょうどいい
- 親密な親子関係が幸せとは限らない
- 子どもの問題は大人が勝手につくっている
- あえて言葉にしないほうが、うなくいくこともある
- 親が社会を否定してはいけない
- 本当の厳しさとは「信用」
- ゆとりのない経験こそが、ゆとりの心を育てる
- 1等賞は称えない
- なんでもかんでも叱らない
- 叱る時は「子ども基準」で考える
- 言葉や態度にしなければ、想いは伝わらない
- 子どもを変える「タイムマシン・クエスチョン」
- 差別する心は消せなくても、差別しない行動はできる
- 嘘も大切なコミュニケーションスキル
- 偽善者でいいんだ
- ゲームに夢中なときだって、生きる道を見つけるチャンス
- 食べ物の好き嫌いがあったっていい
- 汚い言葉遣いから「言葉がどう伝わるか」を考えさせる
- 友達が多いか少ないかは、たいした問題じゃない
- 「習いたがる子」をつくらないことが、子育ての本質
- 家庭学習の習慣は、子どもの時間を奪うだけ
- 特性に縛られすぎてはいけない
- 読み書きが苦手でも、活躍する道は必ずある
- 学べる場所は、学校だけじゃない
- 「読解力」より「伝える力」を磨こう
- 受験に失敗したときこそ淡々と過ごす
- 学校からの呼び出しは、子どもを「叱る」ためじゃない
- 約9割の子どもがいじめ加担者
- いじめは客観的事実で解決に導く
- 本来、子どもは未熟なもの
- 遠慮なく学校、教育委員会と連絡を取ろう
- 全員が当事者になることで教育が変わる
工藤勇一「麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること」から引用
ざっと目を通しただけでも、「えっ?そうなの?」と意外に感じるところや、「常識」や「当たり前」に捉われすぎていたことに気づかされました。
大人も子どもも、皆それぞれ違うのに、いつの間にか枠にはめ込もうとしていたのかもしれません。
「子どもの問題は大人が勝手につくっている」

「子どもの問題は大人が勝手につくっている」
この言葉に、当時の私はハッとさせられました。
小学生になった子どもを見て、周りの子どもたちと比べて焦って不安になっていたんです。
でも、それにアタフタしていたのは自分だけだった、ということもありました(笑)
工藤先生は、「子どもが気にしていないことは、あえて指摘しない」と言います。
心配だからこそ出る親の言葉が、子どもにとってはマイナスになることもある。
大人が問題視していることが、子どものためになっていないこともある。
そう気づかされました。
子どもの話しを深掘りしすぎない

例えば、子どもの友達関係について。
子どもが何気なく話したことから、勝手に推測して深掘りしたり、心配のあまり質問攻めにしてしまうことありますよね。
でも、子どもにしたら、学校で満足して帰ってきたのに、親に質問攻めにされて楽しい気分も台無し。
親の心配そうな言葉が、子どもの苦手意識につながることもあるかもしれません。
子どもの気持ちに寄り添うために、自分の体験から想像してみる
子どもの気持ちを理解しようとするとき、大人はつい自分の経験を基準にしてしまいがちです。
しかし、子どもと私たちは、生きてきた時代も環境も違います。
だからこそ自分の体験を振り返りつつ、子どもの立場に立って想像力を働かせることが大切だと、この本を読んで改めて感じました。
アレルギー体質だった私
子どもの頃からアレルギー体質だった私は、大人になるまでアトピー性皮膚炎に悩まされました。
特に思春期の頃は、見た目を気にする年頃でもあり、人目を気にしてしまうことが多々ありました。
そんな時、身内の集まりで揃って出かけようと準備していたら、親戚の年上の男の子が私の皮膚の状態を見て一言。
「ちょっと汚いから、これで隠した方がいいんじゃないの?」とスカーフを持って来てくれたんです。
彼もその時は未成年でしたし、きっと悪気はなかったんだと思います。
でも「汚い」という言葉だけがグサッと突き刺さり、いっきに外に出るのが億劫になったのを覚えています。
「私は汚いと思われているんだ…」
「隠さないといけないんだ…」
そう感じて、惨めな気持ちになりました。
その後余計に人目が気になり始めたのは言うまでもありません。
この経験から、良かれと思ってかけた言葉や行動が、相手を傷つけたり影響を与えることを痛感しました。
イベント前に熱を出す子どもだった私
また、私は子どもの頃から、イベントの前に熱を出すことがよくありました。
その度に、母は「○○が嫌だからでしょ?」「○○さんと上手くいってないからじゃない?」と、私が思ってもいないことを持ち出して、不調の原因だと決めつけていました。
体調が悪くて辛いのに、さらに追い打ちをかけるような言葉をかけられ本当に辛かったです。
「もしかして、本当に私が悪いのかも…」
そう思って、自分を責めてしまうこともありました。
親戚の男の子とはまた全然違うものですが、親の心配や勘繰りからの決めつけ発言にはとてもストレスを感じていました。
しかも最悪なことに、何か友達関係で嫌なことがある度この言葉を思い出して、少しずつ母の発言通りになっていくんですよね。
ポジティブな植えつけなら良かったのですが(笑)、ネガティブな思考を植えつけられもがいてた記憶があります。
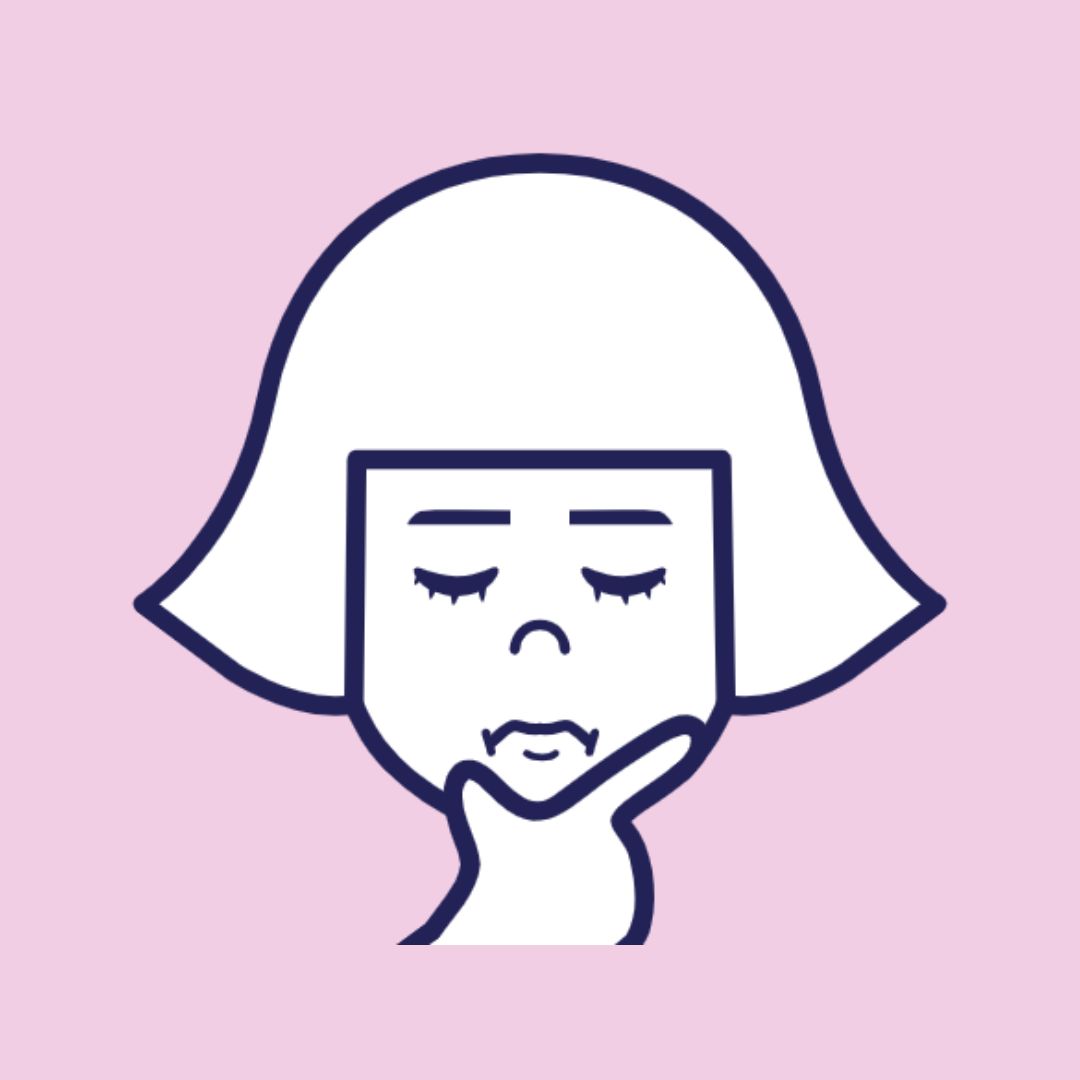
いまだに思い出すと心がギュッと痛くなるんですよね。
自分はこんな刷り込みはしないぞ!と気をつけてはいますが、実際どうなんでしょう(笑)
子どもがサインを出して来たら、一緒に考えたらいい
だから首を突っ込みすぎず、子ども自身に色々な経験をさせてあげたい。
余計な言葉で子どもの心をかき乱すことは、絶対にプラスにはならないので、子どもが助けを求めてきた時や、困っている時に一緒に考えればいい。
ちょっとしたことを大騒ぎすると、子どもはビクビクして殻に閉じこもり、何事も失敗を恐れてチャレンジしなくなるかもしれません。
自分時間や自分だけの空間をお互い大切に
母親は、子どもがいると「できない」「しない」「諦める」「我慢する」が多くなりがちです。
でも、思う存分好きなことに没頭することは、子どもだけの特権ではありません。
大人だって時間を忘れるくらい夢中になって、一喜一憂できるような物事に取り組んで生きていきたい。
イライラ文句や愚痴ばかりの親よりも、毎日楽しくイキイキと充実している姿を記憶に残してあげたい。
子どもに「頑張りなさい!」と言うだけでなく、自分の背中で四苦八苦しているところを見せる方が説得力があります。
他のことに目と意識が向くことで、子どもへの関わり方にもメリハリができて、良い影響があるかもしれません。
見守りではなく監視にならないために
四六時中子どものことを考えて、子どもだけを見ていると悪い面ばかりが目につきます。
特に、子どもが小学校2年生の時に経験したコロナ禍では、学校が長期休みになり自宅でモンモンと過ごしていたからか親子喧嘩も多かったんです。
今思えばちょっとしたことで衝突していたような気がします。
だからこそ「自分だけの時間(空間)を持つ」という意識が強くなり、在宅で仕事をするスペースを変えて別の部屋で過ごしたり、時間の使い方を決めてメリハリをつけるようにしました。
親の目が無い時間が増えてから、子ども自身でタイムスケジュールを決めて動くようになり、意欲や意識が高まった気がします。
子どもだって言葉に出さずとも、「次はこれをしよう!」と決めていることもあるはず。
それなのについつい大人は監視モードになり、必要のない厳しい言葉をかけてしまうんですよね。
これでは子どものやる気も押しつぶされ、結局大人の言葉に流され自分の考えで動く機会まで減ってしまいます。
いつまでも指示待ちする子ではなく、自分で考えて選択する経験を増やしてあげたい。
そのためにも見守ることが大切なんですよね。
読んで正すのではなく視野が広がった!

この本を読んだ後、子どもの関わりに悩んでいた友達に勧めてみたんです。
普段本を読まない友達も、「工藤先生の経験談がベースになっているから、想像しながら読みやすかった!」と言っていました。
先生自身の育児のことや、校長という立場、学校での生徒との関わりからなる言葉や考えは、私の心にも届きやすかったです。
堅苦しくもなく、説教臭くもなく、どんどん読み進められます。
ピシッと正されるようなものではなく、「こういう考え方や捉え方もあるんだな」と視野を広げてもらえました。
人の数だけ個性があるんだから、狭い視野で物事を見ていたら入りきらないのは当然。
「こういうパターンもあるんだ!」「悲観的に捉えなくても大丈夫なんだ!」と、気分が楽になりました。
特に小、中、高校生くらいのお子様のおられる方にはオススメです。
☑親の思っていることが子どものためになるとは限らない。
☑子どものありのままを受け入れてあげよう。
これらのことを、改めて考えさせられました。
↓もしかしたら私は毒親育ち!?毒親のパターンや習性が分かりやすいです
みんなの評価・クチコミは?
【読書メモ】麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること
6/10
日本の学校の先生が筆者みたいな考え持ったら、だいぶ世の中変わってくるんだろうけど。そんな気になる熱意も気力も体力もねえんだろうなとは思う。
自立性・多様性の大事さが分かる本でした。#読了 pic.twitter.com/IdJmK806Bc— ぱぴこ (@semi_puro) March 14, 2022
麹町中校長が教える
子どもが生きる力をつけるために親ができることまだ読み始めたばかりだけど、小6の娘のクラスを思い出しながら💦
子どもの問題は大人が勝手に作っている
まず、子ども同士話し合い学び合いをさせる機会を与えて欲しい
校長、担任の先生のせいばかりにする親が問題を大きくする pic.twitter.com/6QDVVEMM33— lavita (@zoylavita) February 20, 2020
読みました。
ここに書いてある反対のことばかりしてたなぁと、反省しました。少しずつ変えていけたらいいなと思います。
定期的に読み直したいです☺️麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること https://t.co/3BLDv9BUAq
— まめっち (@mamecchi_ad) January 27, 2022
本日のカフェのおともはコレ!
麹町中学校には宿題がないんですってー!衝撃!宿題は手段であり目的ではない。
手段が目的にならないようにしたいですね。麹町中校長が教える 子どもが生きる力をつけるために親ができること https://t.co/9EH5EnyiFq
— トロリーナ (@torori_na96) March 26, 2021
VOD情報
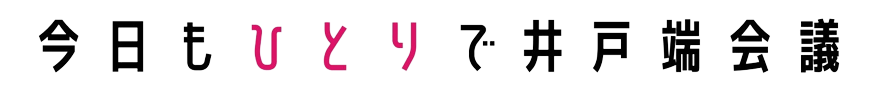
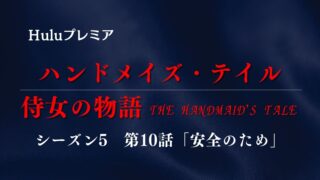
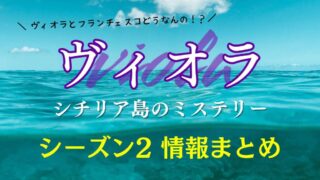




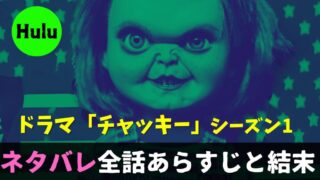
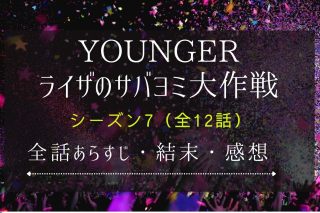

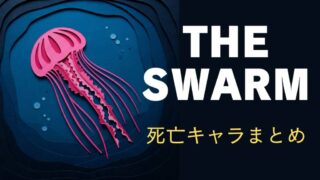
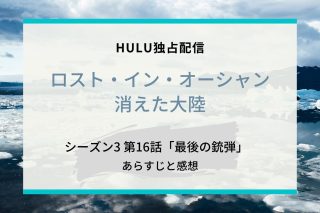
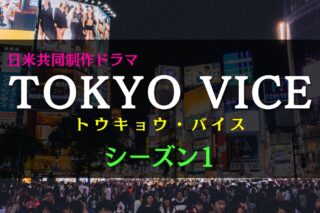


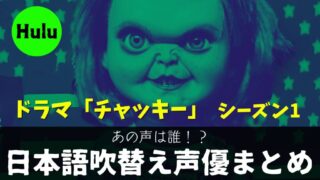

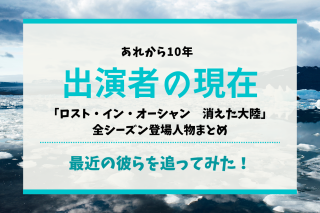






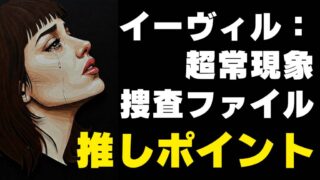

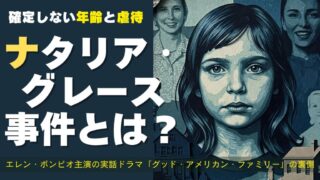

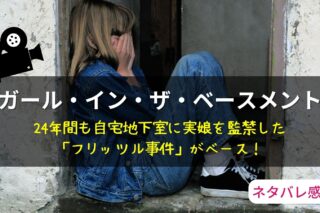


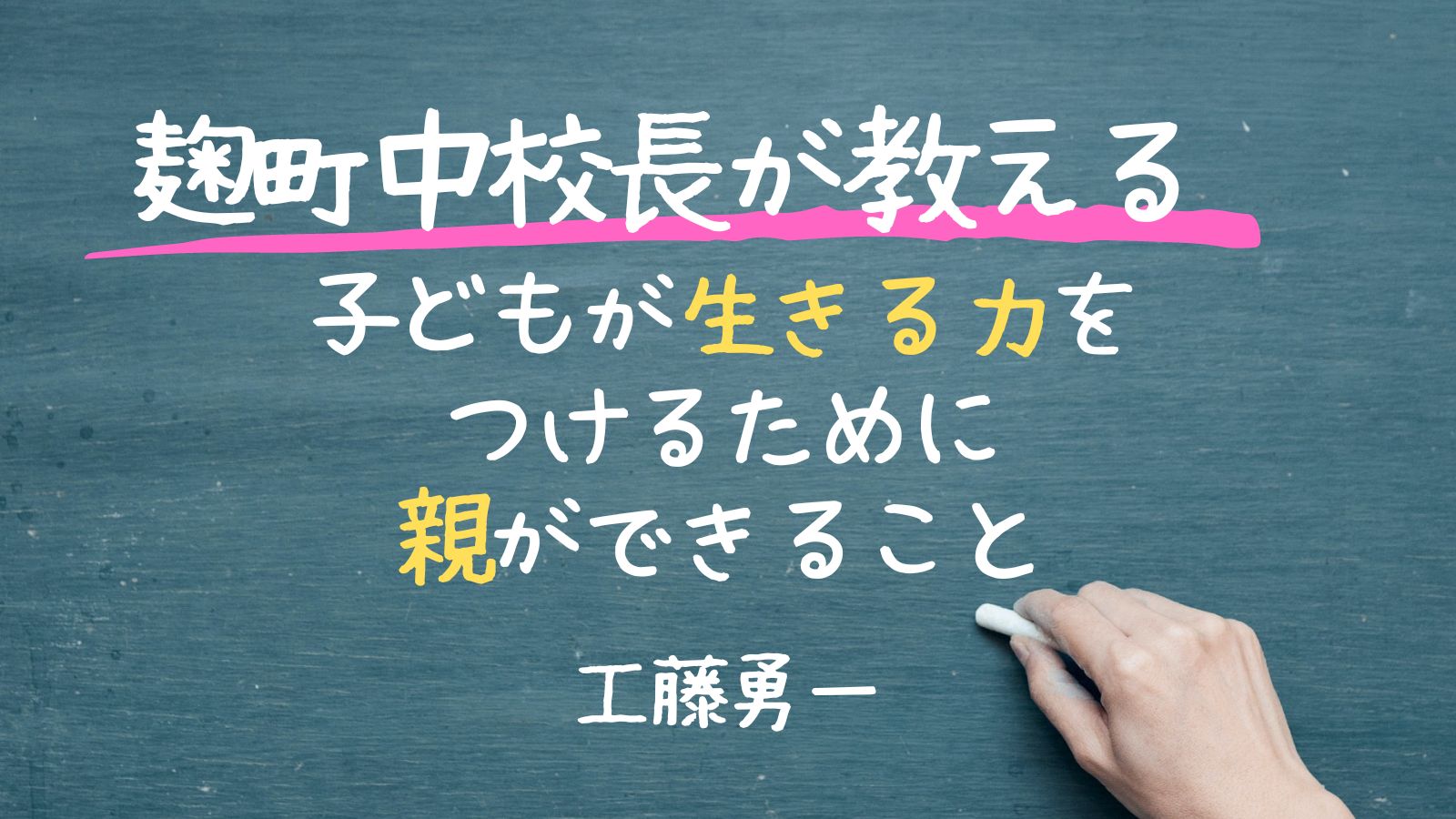






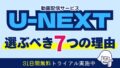
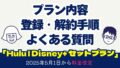

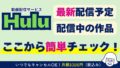






コメント